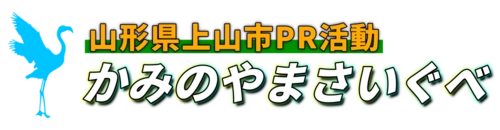「羽前上ノ山 四十八地蔵菩薩」上山を古くから見守る地蔵様・それぞれの場所や御詠歌を紹介
文化十二年又は十四年に成立した四十八地蔵尊巡礼は、時代の変化とともに衰退しつつあります。
願主は利兵衛、発起人は寿仙寺十五世耕雲種月和尚、御詠歌は丸屋専右衛門であるが、開眼された理由は不明である。開眼から二百年以上が経過している今、我々は上山の四十八地蔵尊を認知し、後世に伝えることが必要であると感じる。
第一番 十日町 愛宕堂
愛宕神社の創始は寛永五年、上山領主土岐山城守頼行が城下町の火難防除と五穀豊穣を祈願するために創建したものである。地蔵菩薩は花崗岩を用いた丸彫りである。
| 御詠歌 | さまざまに誓ひおかれしかづかづの願いみちびくここの御やしろ |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像・88cm) |
| 住所 | 十日町11-21 |

第二番 十日町 湯ノ上観音寺
水岸山慈眼院の境内地に位置し、大木下坐像石仏とも呼ばれる。
| 御詠歌 | 湯泉の山の慈悲の御寺に座をしめて猶もらさじとすくふ御仏 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 十日町9-30 |

第三番 裏町 薬師堂
栄町1丁目1-7に架けられている大川橋近くが薬師堂跡地とされているが、知る人は少ない。
当時の薬師堂は、門の右に池、境内に銅造りの地蔵菩薩を安置、左右に石造の地蔵尊を配置しており、左脇の石地蔵尊を「袈裟掛け地蔵」と称した。
| 御詠歌 | 乗りうつる弘誓の船はあひがたきかねの御仏たのめもろ人 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(鉄仏半跏像) |
| 住所 | 鶴脛町2丁目13-5-2 |

第四番 十日町 市神六角地蔵
龕部上は上山大火により欠損、それにより笠と請花・宝珠は後補である。
| 御詠歌 | 市町に神とあがめし六ツのかどむツのちまたをすくふ御仏 |
|---|---|
| 本尊 | 六面石幢(石造単制) |
| 住所 | 十日町2-6 |

第五番 御仮屋脇
堂内には三体の石地蔵が安置されており、信仰の対象物として多くの帽子や着物で覆われている。
| 御詠歌 | 過ぐる日は一日二日三日月の入るさを思ひたのめ後の世 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造坐像) |
| 住所 | 二日町3-5 |

第六番 沢 愛宕堂
木彫の騎馬像「愛宕・将軍地蔵」があったとされる愛宕堂は、現在は存在しない。移転地とされる松山3丁目には、六地蔵尊が安置されている。
| 御詠歌 | 春は花秋は紅葉を見る沢の深く誓ひぞたのもしきかな |
|---|---|
| 本尊 | 不明 |
| 住所 | 松山3丁目2-7 |

第七番 軽井沢 妙正寺
以前は妙正寺と浄光寺の中間に造立されていたが、昭和五十三年、現在の地に再建立したという。
| 御詠歌 | 身に作せし重き罪をも軽井沢妙なる法の寺へまいれば |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像・163cm) |
| 住所 | 軽井沢2丁目1-1 |

第八番 切通 不動堂
台座周辺には小石が多く積み上げられている。その中には穴のあいた石もあり、「耳が良く聞こえるように」「目が見えるように」などの願掛けを行っている証である。
| 御詠歌 | 皆人のまよひのたねをきりどうし不動堂にならぶ御ほとけ |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 新丁2-19 |

第九番 北町 四ツ辻
礎石に中台・台座の上に乗せられ、完全な姿で祀られている。当時、地蔵さまの立っている所は河原であった。
| 御詠歌 | へだてじなみな身うへは北町の四ッのちまたを照らす月影 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 北町本丁2-11 |

第十番 川向 出張
三体の地蔵尊と単制の六面幢が一基、安置されている。紀年銘文が確認できないため、いずれも詳細は不明である。
| 御詠歌 | 彼岸に今ぞいたらん川むかひ弘誓の船の棹をたのみて |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 八日町9-1 |

第十一番 松山 稲荷堂
元は東側の高台に安置されていたが、六面幢とともに地蔵尊が移転されてきたとされる。地蔵さまの頭部は別個に造り替えたものである。
| 御詠歌 | 緑さす恵みぞしるき松山の稲荷もおなじ御仏の縁 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 松山2丁目6-34 |

第十二番 河原期 熊野堂
熊野神社は、大同元年の創始という古い伝承があり、高楯城の防御の役割を果たしていたという。
| 御詠歌 | のちの世を願うは今ぞ今熊野はやかはらごに罪はながるる |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 河崎高楯259 |

第十三番 石曽根村
台座の周りには浅い蓮弁を施しており、中台は凝灰岩を用いている。
| 御詠歌 | 後の世を願ふ心は軽くとも仏のちかひ重き石曽根 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像・120cm) |
| 住所 | 石曽根1352-1 |

第十四番 川口 寝覚
市内では珍しい軟質な凝灰岩を用いており、以前は台石が地面に埋められていた。
| 御詠歌 | 明け暮れにたゆまずたのめうば玉の夢の寝覚めに立てる御仏 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像・214cm) |
| 住所 | 川口山際48 |

第十五番 小穴 浪形山
蓬莱の薬師堂は大勢の参拝者で賑わっていたため、堂の周りには多くの「穴あき石」が供えられていたが、今は見当たらない。地蔵さまの頭部は欠損により、円い石に換わっている。
| 御詠歌 | 無漏の海深きちかひをたのめてもたつや真如のなみがたの山 |
|---|---|
| 本尊 | 地持地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 小穴1 |

第十六番 小穴 大沢山女人堂
女人堂が小穴に在ったという資料は残っておらず、詳細は不明である。
| 御詠歌 | 三つ五つ障りある身も捨てしなくたすけたまはん大沢の山 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 小穴85 |

第十七番 阿弥陀地 阿弥陀堂
阿弥陀堂境内に造立され、四角い台石に中台を配し、上に蓮弁を施した台座に地蔵尊を安置している。
| 御詠歌 | 阿弥陀地の千草の花におく露の玉しく敷く野辺や浄土なるらん |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 阿弥陀地1065 |

第十八番 藤五 明神堂
藤五とは藤吾のことである。鹿島神社の境内地に安置されており、今も根強く信仰されているという。
| 御詠歌 | むらさきの雲の迎ひをしめしてや藤五つもとに立てる御仏 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 藤吾道上1566 |

第十九番 上田中 一本仏
昔、下関根村には「つらきれ地蔵」という高さ165cmほどの自然石があったという。
現在は、土地改良区により跡形もなく水田になっているが、移転地には、坐像の地蔵尊と自然石卒塔婆が造立されている。
| 御詠歌 | ただたのめ田中に生ふる蔦かつら誓い導く御手の糸とも |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石仏坐像) |
| 住所 | 関根28 |

第二十番 下関根 出口
地蔵尊は二体とも類似しているが、彫り方が僅かに違う。
「やめ地蔵」と呼ばれることもあり、目やにが溜まって不自由になった時、お参りをすれば治して呉れるという。
| 御詠歌 | 罪とがわ長月におく下関根きゆる朝日の御名をたのまん |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 関根65 |

第二十一番 中関根 中興寺跡
中関根に建立されていたという中興寺についての詳細は不明であり、跡地は果樹園となっている。
地蔵尊の台座は手の込んだ手法を用いており、隣接している建物は、個人持ちの阿弥陀祠である。
| 御詠歌 | 善し悪しのその中道の関の戸は仏の御手のすくふなるべし |
|---|---|
| 本尊 | 地持地蔵菩薩(石造坐像) |
| 住所 | 相生784-6 |

第二十二番 上関根 願王山延命寺
文政三年頃、和尚の枕元に霊石が現れて、「寺の裏の林中を掘って貰いたい」と云って消えたという。そこで、掘ってみると巨石が出現。寺まで運搬しようとしたところ、突然、数万匹の鼠から襲われ、寺の門まで慌てて逃げると、何と、鼠が次々と消え去った。
その霊石は現在、「延命地蔵尊」と刻まれ、山門に立っている。
| 御詠歌 | ありがたや飢へずこごえず二世かけてよわひをのぶるちかひありとは |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 三上12 |

第二十三番 皆沢 龍谷寺六地蔵
返り花を施した台石と蓮弁付きの蓮台に、六体の地蔵尊が安置されている。重制六面幢の龕部と地蔵講中による遺品も残されている。
| 御詠歌 | 皆沢の龍の谷水たへせぬは六つの仏の誓へなるべし |
|---|---|
| 本尊 | 六地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 皆沢22 |

第二十四番 楢下 福聚寺
天台宗如意山福聚寺が建立されていた地であり、大きく開花した蓮弁を台座に坐像の地蔵尊を安置している。
| 御詠歌 | 夏山の楢の下葉をふく風はかの世涼しきほだしなるらん |
|---|---|
| 本尊 | 地持地蔵菩薩(石造坐像) |
| 住所 | 楢下59 |

第二十五番 小笹 小豆森
天台宗如意山福聚寺が建立されていた地であり、大きく開花した蓮弁を台座に坐像の地蔵尊を安置している。
| 御詠歌 | 夏山の楢の下葉をふく風はかの世涼しきほだしなるらん |
|---|---|
| 本尊 | 地持地蔵菩薩(石造坐像) |
| 住所 | 楢下59 |

第二十六番 大門 極楽堂跡あみだ堂
現在、極楽堂跡は畑地となっているが、昔は幾つかの石造物があったという。その石造物については、阿弥陀堂境内地へ移されたと推測されるが、台石は不明である。
| 御詠歌 | 楽しみを極むる寺にましまして知るも知らぬも救い御仏 |
|---|---|
| 本尊 | 不明(石造) |
| 住所 | 大門22 |

第二十七番 菖蒲沢 おはた坂上 山神堂
管理が行き届いている場所ではあるが、詳細は不明である。
| 御詠歌 | 賤がうむ荢綿坂にも跡たれて縁の綱でを結ぶ御仏 |
|---|---|
| 本尊 | 不明(石造) |
| 住所 | 大門70-1 |

第二十八番 須田板 地蔵堂
背に光輪を配し、厨子の中に安置されているが、全体的に欠損が目立つ。過去に、地蔵さまは火災に遭っている。
| 御詠歌 | 身に積みし罪をも何と須田板や信こころに願うもろ人 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(木像坐像・20cm) |
| 住所 | 須田板12 |

第二十九番 原口 うえの山薬師堂
境内に単独の地蔵尊は見当たらず、墓石に用いられた一体と、二基の六面幢が造立され、いずれも崩れ残欠となっている。
| 御詠歌 | みな人のむさぼり多き原口や諸病悉除の願はありとも |
|---|---|
| 本尊 | 六面石幢(石造重制) |
| 住所 | 原口830 |

第三十番 如来寺旧地六角
全国でも例を見ない五面に冥府の十王と見られる内の五王と、腰をおろしている姿の邪鬼が彫られ、龕部に六地蔵尊を配す。
「仏説地蔵菩薩発心因縁十王経」による彫りの信仰であろう。
| 御詠歌 | 後の世の種をまきのと聞くからに世をふる寺の跡をたづねん |
|---|---|
| 本尊 | 六面石幢(石幢重制) |
| 住所 | 牧野1378 |

第三十一番 上生居 観音堂六角
地蔵尊の台石は見当たらず、頭部の請花と宝珠は欠損し不明である。
| 御詠歌 | 御仏に縁を結ぶの上生居後の世この世たのもしかな |
|---|---|
| 本尊 | 六面石幢(石造重制) |
| 住所 | 上生居492 |

第三十二番 中生居
以前は、少し離れた祠に安置されていた様であるが、三十三観音第二十三番境内地に移されている。
祠に安置されていたためか、六面石幢の状態は良好である。
| 御詠歌 | 憂きつらきかかる浮き世の中生居二世安樂を祈りれもの人 |
|---|---|
| 本尊 | 六面石幢(石造重制) |
| 住所 | 中生居25 |

第三十三番 下生居
算盤の珠と似た中台に、舟形に彫られた地蔵尊が墓石に用いられ造立されているが、その中台が講中によって造立された地蔵尊の残欠である。
| 御詠歌 | 世にすめばあらぬ業を下生居とく世をいとひ後を祈らん |
|---|---|
| 本尊 | 不明(石造) |
| 住所 | 下生居348-2 |

第三十四番 子育地蔵尊
光背型の法印地蔵尊は子育地蔵や安産地蔵とも呼ばれ、子供が無事に生まれ、丈夫に育つ様にとお参りに来て、前掛けを掛けて行く人もいるという。
| 御詠歌 | 親よりも深き恵みを忘るなよ御名の乳房を口にふくみて |
|---|---|
| 本尊 | 法印地蔵菩薩(石造光背型) |
| 住所 | 宮脇278 |

第三十五番 射留 宿尻地蔵尊
付近を宿尻と呼ぶことから、宿尻地蔵とも称される。道路沿いに位置しているものの、地蔵さまの存在に気づく人は少ない。
| 御詠歌 | よしあしももらさで救う御仏の御手の射留にたよれもろ人 |
|---|---|
| 本尊 | 地持地蔵菩薩(光背型立像) |
| 住所 | 仙石屋敷裏403-1 |

第三十六番 仙石 高仙寺
仙石は急坂に出来た宗教集落で、高仙寺は集落の高台にある。
最上四十八地蔵第十三番の地蔵堂横に位置する、「施主 講中」と刻まれた台座を上山札所と見る。
| 御詠歌 | 世のわざをとやせんかくや仙石の寺へまいるも後の世のため |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 仙石屋敷裏1 |

第三十七番 馬立 金峰山蔵王堂
蔵王堂とは刈田嶺神社のことである。数百年にもなる銀杏の古木が植えられ、蓮弁を施した台座に、地蔵尊坐像の半分が乗せられている。
境内には、その他にも石造物が複数存在する。
| 御詠歌 | あら尊とこ金の峰の山のこし鐘の響きにあくる東雲 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造坐像) |
| 住所 | 金谷26 |

第三十八番 甲石 雷神堂前
台石は蔵王川の安山岩を用いて、中台と蓮弁を彫った台座を乗せ、地蔵尊を安置している。
| 御詠歌 | 天地の恵みは同じなる神にならひて世をやすくふ御仏 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 金谷甲石455 |

第三十九番 高野 大師堂前
弘法大師堂は文政七年の洪水により流失。五年後に再建したものが現在の堂である。
| 御詠歌 | 後の世は楽しみながき永野なる里に居まして救う御仏 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 高野高野原165 |

第四十番 永野 太子堂
聖徳太子を祀る太子堂。聖徳太子は、職人達の本尊であるため信仰も厚く、特に中川地区でも蔵王川流域で活動した石屋職人の信仰が厚かった。
しかし、肝心な地蔵さまは太子堂境内には造立されていない。
| 御詠歌 | 後の世は楽しみながき永野なる里にいまして救ふ御仏け |
|---|---|
| 本尊 | 不明 |
| 住所 | 永野54 |

第四十一番 高野 薄沢
当地には多くの石造物が寄せ集められ、造立されている。
「御詠歌」の地蔵尊は、頭部が新しく造り替えられており、中台には連子紋様を陰刻に彫り付けている。
| 御詠歌 | みな人の願ふ心はうすくとも助けたまはん御名ぞ尊とき |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 高野薄沢21 |

第四十二番 権現堂 釈迦堂
欠損によって再造立されたためか、石幢の状態は良好である。
| 御詠歌 | あら尊と導きたまふちかひにや権に現れいます御仏 |
|---|---|
| 本尊 | 六面石幢(石造重制) |
| 住所 | 権現堂地蔵堂74-4 |

第四十三番 金谷 三ツ辻
自然石を用いた台石の上に中台・台座を乗せて、地蔵尊を安置している姿は完全である。
| 御詠歌 | おそろしき六つの巷にましまして三つの巷を救ふ御仏 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 金谷15 |

第四十四番 小泉 入口
付近には幾つかの石造物も見受けられ、その状態の良さから、信仰の厚さを感じさせられる。
| 御詠歌 | 法の水いでて流れる小泉の深く誓いをくめや諸人 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 泉川1 |

第四十五番 同川向 弁天森
今は住宅地である弁天だが、当時は森であったと思わる。地蔵尊の台石や中台は不明であるが、頭部は新しく造り替えられたものである。
| 御詠歌 | 御仏の慈悲は同じとわきまえて歩みをはこぶ天のもりかな |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 弁天2丁目3-56 |

第四十六番 外原 一ツ松前
六面幢は重制であるが、完全な石幢ではない。
| 御詠歌 | 御仏の慈悲は同じとわきまえて歩みをはこぶ天のもりかな |
|---|---|
| 本尊 | 六面石幢(石造重制) |
| 住所 | 四ツ谷2丁目2-70 |

第四十七番 四ツ谷 大日堂前
四ツ谷に建立されている大日堂は元和九年の創建であり、境内に造立されている庚申一座塔は、上山市指定文化財である。
| 御詠歌 | 幼な子の一つや二つ三つ四ツや仏の前に塔をつむ石 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 四ツ谷1丁目2-43 |

第四十八番 花立 地蔵堂
久保手に通じる花立峠の頂に造立されており、当時は木像の地蔵尊を安置していたと考えられている。
| 御詠歌 | 春つつじ夏はあやめに秋桔梗たえず手向の法の花立 |
|---|---|
| 本尊 | 延命地蔵菩薩(石造立像) |
| 住所 | 北町外原1469-5 |