
【上山市の祭りの原点】380年以上続く伝統行事「三社神輿渡御行列」をご紹介します

寛永18年、上山城主土岐頼行は徳川家綱の誕生を祝し、旧暦8月14日から16日まで正八幡神社と八幡神社の神輿を城下に渡御して、「武運長久、天下泰平、五穀豊穣」を祈願したことから始まりました。その後、元禄10年に城主は松平信通に変わり、賑やかな行列を取り入れ山車屋台も出し、大勢の人が集まったと伝えられています。また、将軍家公認の祭りであったことから、参勤交代で諸大名の通行と言えども行列を遮ぎること、高い所からの参拝などが禁じられていました。
明治4年、廃藩となり祭りは取りやめになりましたが、明治11年に月岡神社創建、伝統の祭りを正八幡神社・八幡神社と共に復活、鼓笛楽隊や甲冑隊と稚児隊も加わり、「国家隆昌、世界平和、家業繁栄、商売繁盛、家内安全」を祈願、現在に受け継がれています。三社神輿渡御行列は上山の祭りの原点、380年以上の歴史と文化を伝える遺産として、他に類を見ない貴重なものであり、次世代に守り伝えていかなければならない。
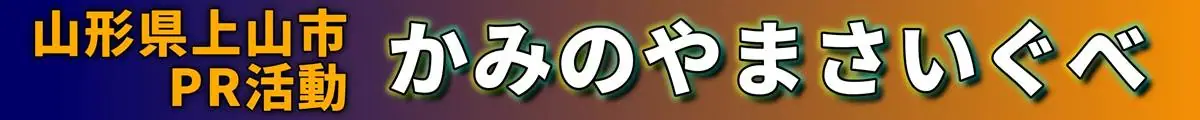 上山市の観光から生活、イベントや公園、子育てやレジャーまで、ジャンルを問わず様々な役立つ情報を発信しています。
上山市の観光から生活、イベントや公園、子育てやレジャーまで、ジャンルを問わず様々な役立つ情報を発信しています。www.kaminoyamasaigube.com
【メンバー募集中!】
協力して上山市のPRに取り組みませんか?









